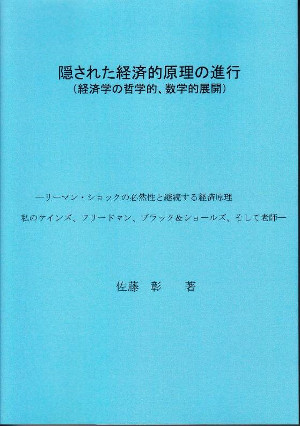[Ⅰ]本書の内容の若干の紹介
(1)私は1990年代にケインズ主義の総括的反省をやらなければならないと考えた。
本書第1部の第Ⅱ篇は、1999年に書いた「ケインズ批判論文草稿」の追加と改訂で、ケインズへの尊敬と批判的検討である。
セイの法則の仮説の検討から始まって有効需要論、つまりケインズの原理論を批判した。またそれがどのように危機を招き寄せたかを明らかにした。それは、ケインズの理論への批判的検討を数学の方法で全面的に批判したものであり、セイの法則とケインズの完全雇用論とが成立不可能なことを数学的方法で明らかにした。
また、ケインズのイデオロギーが恐慌の問題を本当に解決するのか、価値法則、資本蓄積論、固定資本論から論じた。とくに景気循環との関係で、M=k・P・Yの現金残高方程式(ケンブリッジ方程式)に現れるマーシャルのkの特別な意義を再検討した。
第Ⅳ編はマネタリズム批判である。シカゴ学派であるM・フリードマンに代表されるマネタリストの考え(「貨幣数量説」)とその恐慌論を批判した。とくにフリードマン派の「Q/Vが長期的安定」という仮定、つまりQ/V=Tとしてマネー・M(T)=Tは動かない不動点(Mは恒等写像、変換)であるか否かを調べ、不動点でないことを明らかにした。
生産資本の回転と擬制資本のそれぞれの流通加速度から、紙幣貨幣数量の増大が投機以外になりえないことを明らかにし、最近のマネタリズムの紙幣貨幣量増による実質GDP拡大論を批判した。そこでは、外部からの紙幣増による利子率r→0つまり利潤率の著しい低下のもとでは、紙幣を増大させても、物価上昇と生産への寄与とはならないことを明らかにした(消費税や関税による物価上昇は論外)。同時に貨幣選好論の限界を示し、ケインズの利子率論を批判した。
(2)第2部第Ⅰ篇は擬制資本論である。
1)「我々が分からなかったのはサブプライムローンなどの与信がどれだけ危険にさらされているのか分からなかった」というバーナンキ氏の発言をテレビで聞いたことがある。 現実資本と擬制資本(架空資本)との矛盾の進展、擬制資本と貨幣との擬制的同値関係の破れの法則とリスク関係の深淵が分からなかったということであろう。リーマン・ショックとは、住宅担保証券、CDSなどのあらゆる債券が貨幣(実は紙幣)との想定されている同値関係が破れ、世界的な金融危機を招来したことである。現在でも2008年金融危機の後遺症に悩んでいる欧州の銀行は多いというし、ECBは南欧州の銀行の倒産危機を支えている。FRBも米国債の過積の上にさらに住宅担保証券を積み上げている。これは由々しき難問である。
マンデルプロ氏は「金融工学」は「砂上の楼閣」という(「禁断の市場」(東洋経済新報社))。ジョセフ・E・スティグリッツ氏は「2008年から2009年にかけての世界金融危機ではデリバティブ市場が中心的役割」(「世界の99%を貧困にする経済」P99)を果たしたという。
本書第2部では金融と現実資本との相互関係と矛盾を扱うが、2008年の金融危機の原因と通説化されている金融工学、その中心理論となっていたB&S偏微分方程式の批判を中心として金融を論じる。
B&S方程式は「ウィナー過程」を取り入れることによって成立している。伊藤清氏の「確率論」(岩波数学選書)には伊藤氏の確率や確率過程論の数学的功績が論述されている。B&Sが飛びついたのは、第5章 5.14「確率微分方程式論の直感的背景」以下のすばらしい論述である。「fn(Xn,Bn+1)が実際Bn+1を含むならば、この方程式は変動Xn+1-XnがXnの値以外に偶然的影響を含むことを意味する。」「(例えばWiener過程B={Bi}としておこう)という「Wiener過程」である。株価の変動に「Wiener過程」を適用する根拠は全くないにもかかわらず、バイアス的に「(例えば)」に飛びついた。
「ウィナー過程」とは、ブラウン運動の物理的背景・力学関係(物理学)が作り出す数学的問題、確率過程である。アインシュタインのブラウン運動理論には分子運動論、熱平衡、浸透圧などの明確な物理的根拠、背景がある。BS方程式には明確な経済的背景がない。つまりBS方程式にウィナー過程を利用する合理的理由はない。株価変動に「ウィナー過程」を適用するレトリックはまちがいである。BS方程式→拡散方程式→正規分布は株価の確率法則とは原理上なりえない。BS方程式はもともと正規分布を前提としているといってもよいのが、抽出、採用された「理論分布としての正規分布」と経験分布(現実のデータ)とはフットテールの存在などによって実際は背離している。とりわけ決定的なことは、σ:一定との仮定そのものによってボラティリティが論外にされていることである。
2) さらに問題なのは、取引戦略の自己資本充足的という問題の崩れである。
M&B方程式の「ポートフォリオG(t)の利得とオプションfによる利得と同じようにする]という要請の問題である。
金融派生商品の価格をf(S、t) 、Sを株式の株価、B債券価格とする。
B&Sの2階偏微分方程式においてr(利子率)→0つまり、r≒0とすると、右辺は0で、f(S、t)はそれこそ市場価値の変化のみのリスク商品となる。B&S論のロジック、レトリックの危なさである。
一般的にいえばP(S)とP(rB)はそれぞれ部分的な量的、質的変化をしており、ポートフォリオのP(S∩rB)の一時的な自己対称性、またP(S∩rB) ∩P(f(s、t))の自己対称性もf(S、t)の激しい変動性のもとで破れる。
市場価値の変化のみでf(s、t)派生商品価格と一致させることができるという派生商品価格の形成は自己矛盾を極めている。一般的にいえばP(S)とP(rB)はそれぞれ部分的な量的、質的変化をしており、ポートフォリオのP(S∩rB)の一時的な自己対称性、またP(S∩rB) ∩P(f(s、t))の自己対称性もf(S、t)の激しい変動性のもとで破れる。ポートフォリオにおいてP(S∩rB)のrに添字iを付加し、(ri)とすればSとriBiとの同時存在の崩壊の可能性は高まる。キャリーキャッシュなども不安定になる。Δヘッヂイングなど存在しなくなる。市場価値の変化のみでf(s、t)派生商品価格と一致させることができるという派生商品価格の形成は自己矛盾の極みに陥る。
以上のように 株価は、BS方程式と正規分布では表現できなかった。 そこで株価の変動が激しい局面の原理を探求するために、第2部では「大恐慌への移行の数学的考察―価値法則への反映的な株価の収束」などの章で経済法則と測度論、ラドン・ニコディムの定理などで景気循環の数式Ktをたてた。それは産業循環(経済循環)に規定された「マーシャルのk=一定」というものからの飛躍、止揚である。
3)(1)古典的景気循環と株価
古典的景気循環では、商品価格W(tk4)は恐慌・不況(tk4)での商品価値ω(tk4)の範囲を反映してω(tk4)≒W(tk4)に収束する。株価格も、ω(tk4)≒W(tk4)に対応して信用の崩れとともに株価格S(t)↓と暴落する。これらは、当該社会関係が受け入れ可能な状態まで価値崩壊もおこることである。それから遅遅たる停滞局面となる。これが大恐慌のプロセスである。日本の90年代ではケインズ政策の累積で恐慌、不況は大規模であり、信用崩壊も大規模であった。株価格S(t)の停滞も長期にわたった。
古典的景気循環には本書では、それぞれ局面があるとし、それぞれの局面の価格Wkの傾向があり、Wとωとの背離過程と爆発、一致過程を示すことになるし、局面における価格Wkと株価格S(tk)との区別と関連から局面の株価の期待値と偏差を過去のデータから抽出、学習することができるとした。 また株価の変動の諸原因、諸事象を株価上下のいわば【隠れた】変数群としてベイズ的試行の試みにもふれた。 しかし、古典的景気循環の時代は質的変化した。
(2)利潤率低下と利潤量の増大との相補性の破れと株価(予測分布)
しかし、現在は利潤率低下と利潤量の増大の相補性が破れている段階である。古典的循環の時代ではない。 利潤率の歴史的傾向的低下の時代の特徴が株価、債権の上下運動にも反映する。それらは利潤率傾向的低下と、したがって利子率低下、政策金利と紙幣増刷に依存する。しかも投機の限界効率も作用する。政策金利や紙幣増刷によって利潤率のゆらぎ↑↓や突出と陥没を繰り返そうとも、利潤率低下と利潤量の増大の相補性が破れている利潤率の歴史的傾向的低下の時代の特徴が株価、債権の上下運動に反映する。
ベイズ推定などの書籍などを参照すると、
予測分布:θはパラメータ、データDで、未知の値χ*を求める場合
、
予測分布P(χ*|D)=∫P(χ*|θ)P(θ|D) dθとある。
ここで「マーシャルのk」の止揚であるKtをもちいる。データDがすでに手元にあり、未知の値χ*を求める場合について考えると、株価は景気循環に依存するから、パラメータθを景気循環Ktにすると、株価の上下をS、求める未知の値s*とすると、
予測分布P(s*|S)=∫P(s*|Kt)P(Kt|S) dKt・・・(K.1)
さらに、利潤率低下と利潤量の増大の相補性が破れている時代では、政策金利や紙幣増刷によって、とくに紙幣増発は恣意的に無限増発されると利潤率のゆらぎ↑↓には限りがあるとはいえ、株価も一定の時期左右される。政策金利や紙幣増刷をβとすると、P(s*|β)(金利上下や紙幣量上下のもとでのs*の確率)と(K.1)との積の傾向となる。
しかし、価値増殖過程と相対している交換過程には、人間の利殖欲望が介在しており、例えば戦争に利益をもつ人々もおり、数学で解しきれない諸矛盾によっても変動する。利潤率の歴史的傾向的低下の時代では、なおさらである。
また現在は利潤率低下と利潤量の増大の相補性が破れている段階、したがって利潤率傾向的低下から「マーシャルのk」の止揚であるKtを利潤率に従属する関数として、利潤や時間で偏微分すると、利潤に関しては、超過利潤以外は変化をもたらさない。そこで、この段階では、株価は、超過利潤、利子率、為替、国家間の対立、階級矛盾等の展開によって上下の影響をうけることのみとなる。
そして、そこでは擬制資本の擬制化の加重化と膨大発行によって、現実資本の運動に対して架空化が進行し、破綻の可能性が増大する。それらはリーマン・ショックで見た通りである。
また利潤率低下による労賃低下、失業増大および資本の海外移転による国内矛盾の激化による保護貿易主義による諸外国間の政治的対立と戦争の可能性がもっとも株上下に影響する。利潤率低下と利潤量の増大の相補性の破れの時代、利潤率の歴史的傾向的低下のもと、株価、債権の変動、擬制資本の擬制化の加重化と膨大発行によって、現実資本の運動に対して架空化が進行しているとき、株価上下の条件事象、【隠れた】変数群の中の戦争等が擬制資本の変動に主要に、ある時は決定的に作用する。
4)パリパ・リーマンのデリバティブ恐慌(擬制資本の同値関係の破れ)
株、金融派生商品などは現金との交換量の変動のみならず、架空化、擬制資本化につれて相互到達(相互変換)が不可能に陥る現実的可能性をもっている。即ち同値関係の喪失の可能性である。
人々の意識と行動原理は、その抽象的可能性としてのみ感覚し、現実的可能性としての意識は希薄であるため取引は発展する。それを「理性」として、ヘッジとして「保証」したのがB&S方程式などであった。
抽象的可能性を確率と捉えるとき、その現実的可能性への転化の諸条件や実現値を前もって捉えることは余りにも複雑である。抽象的可能性を確率と捉えるとき、例えば擬制資本類をマルコフ連鎖的(条件付確率において、現在の状態X n=iが起こった後には必ず次はXn+1=jとなる確率過程)を擬似的に見ることなどが起こりそうである。このような時、n≥0のnが特定の自然数の時にi→jとなる予想、またjでもzになる予想、思惑、勘などによって「現i」から立てられなくなる時、心理的不安が波立つ。それが継続し、部分的なら小恐怖であり、全面的ならパニックに陥る。
擬制資本の同値関係の喪失の現実的可能性は、擬制資本化の加重の程度が拡大すればするほど高くなる。しかし、B&S方程式はヘッヂを「保証」した。同値関係の喪失のそれが現実となったのが、パリパショックに続くリーマンのデリバティブ恐慌である。リスク回避商品による金融のリスク増大という皮相な結果と、予期せぬ金融の博打状態が現出した。
その結果、架空化、擬制資本化の加重化につれて相互到達(相互変換)即ち同値関係の喪失の現実的可能性が現実になった。アメリカ国民の自宅の価格が半額化し、国民の1/3が住宅ローンで損失し、株価が暴落し、銀行のほとんどが危機に陥った。有力な大企業(電子・IT企業、自動車企業)でさえ危機に陥った。
5) 境界条件の除去と紙幣発行の任意性
(1)境界条件
第一の境界条件は、労働者の再生産費であり、自然律(自然率)であり、再生産条件の均衡条件であり、労働力再生産費は自然律・率であり、いわば境界条件である。これによって、景気循環=資本蓄積の局面推移(恐慌、不況→活況→繁栄→恐慌の繰り返し)という運動が保証されている。
ところが、境界条件の除去がフリードマンなどの紙幣の出し入れのみの「純貨幣的」経済学者の登場と支配によってはかられた。フリードマンは、「法定最低賃金」や福祉などの社会政策は全く必要ないものとした(「資本主義の自由」)。労働力再生産費という自然率という「底」が取り除かれると経済は永続的な不安定運動(非平衡運動)となり、あらゆるところで不均衡が拡大する。そこでとんでもない商売が登場する。支払い能力のない貧民を対象とした住宅ローンによるリーマン・ショックはその典型である。
利子率がケインズ派の下限定理以下に低下した場合、一定の時期には、蓄蔵よりも投機的な貨幣需要が増大する。生産過程に固定されている資本の回転と投機的な擬制資本とは、流通速度がそもそも違っているが、投機的な通貨が量的に拡大し、また流通の加速度が増し、株価も高騰する。今度は、利子率が上がると、擬制資本の市場価格が下がる。利潤率低下と真逆方向の利子率↑は、株価が下落し、市場と軋轢を生む。
さらにトレーダーの主観的評価である参照点を超えると「評価価値」も下落し、市場価格が一層暴落する。交換過程からみた破綻である。ファンドが一夜にして消滅する場合もある。株価に情報の全てが反映していると仮定されている市場合理仮説の認識も崩壊する。(2)紙幣の恣意的、無制限のプリント
発行当局の紙幣増発と資本蓄積による利潤率の原理とは、全く異なる当為である。蓄蔵貨幣と全く異なる、通貨発行益(シニョリッジ)による「擬制資本形成」は、対価なしの印刷(印刷費)のみで「資本形成」を謀るものである。
当初は世界的恐慌の拡大を防ぐための「最後の貸し手」としての支払、流通手段としての紙幣の供給であったが、FRBによる住宅担保証券の購入へと進んだ。09年からアメリカFRBは貨幣との同値関係を失った住宅担保証券などとドル紙幣を交換し、財務証券住宅担保証券など膨大な債権、債務の清算問題が絶えず浮上し、債務上限問題がアメリカの政治問題となっている。FRBの保有債券残高は、天文学的であり、債券残高縮小の過程があれば、利潤率低下の歴史的傾向の中で利潤の分割の一部である金利は、債券市場の変化とともに短期、長期のそれぞれの振れは金融市場の変化への動因となろう。
FRB同様に、日銀も毎年80兆円の国債を購入し、国債、さらにETF、REITと紙幣を引き換え、市中に供給して現状の再生産を続けている。日本の異次元緩和というものは、数年来の通貨発行益(シニョリッジ)による国債、債券、株購入による「擬制資本形成」であり、擬制資本の高騰形成であり、現実資本との矛盾の潜在的巨大拡大である。通貨発行益(シニョリッジ)による中央銀行資産の巨大擬制資本化と市中の擬制資本高騰形成は、現実資本との矛盾の拡大であり、デフォルトの潜在的可能である。デフォルトの潜在的可能が現実に転化する前に、国民への税金先取り請求権(国債の堆積)から増税を実行せざるをえなくなる。(デフォルトが現実化しそうな時には戦中、戦前のときと同じような紙幣の恣意的、無制限のプリント策の継続しかありえない。)
現在の景気動向は、古典的循環とは明らかに違う。特に2007年のリ―マン恐慌以降、鉱工業生産指数は上下運動の振動数が多くなっており、振動数の過多とともに減衰していく様相を呈している。本書の中で展開されるΔW(商品価格)≒Δω(価値)の長期傾向のもとでは、金利、紙幣の増発、為替変動、対外貿易変動などからのみ生産指数が影響をうける。当然にも鉱工業生産指数は上下運動の振動数が多く減衰的である。明らかに古典的景気循環は変容した。また逆イールド現象が頻繁に起こるようになっている。利潤率低下、r→0の時代、混迷する現実資本に反して架空資本は増大し続け、現実資本との矛盾は常に臨界点にある。金融恐慌の存在確率は当然高くなる。
[Ⅱ]本書の内容と現代
この著作の目的は、「利潤率低下と利潤量増大」との「相補関係の破れ」とその「反作用」という因果関係を見るとともに、確率論的にも社会・経済現象の変化をみていくことにある。
現在は、一方では先進資本主義のIT経済の進展と超過利潤のためのIT電子技術の熾烈な競争であり、他方、グローバル化による国内矛盾は、各国間の矛盾の拡大、貿易戦争の拡大を引き起こしている「波乱の時代」である。
先進資本主義諸国の利潤率低下に反作用する資本行為=国内労働者の低賃金化、移民の活用による利潤の獲得、とくに生産の海外移転による国内産業の空洞化と失業、これらによって貧富のかつてない拡大での国内矛盾が爆発している。つまり、「利潤率低下と利潤量増大との『相補性(相補関係)』の破れに伴う超過利潤獲得競争(グローバル)よって先進諸国の国内矛盾が爆発している時代である。
保護貿易的傾向を強めている米国、イギリス。またEUという統一通貨と共同市場で利益を享受している国と敗者との分裂傾向。世界貿易を必要としている中国、また日本のように輸出と海外生産に依拠する国々の自由貿易主義。とくに悲惨なのは、資本が引き上げられ危機(通貨下落とインフレ)に陥っている低開発国、資源だけを取り上げられる資源単一国。これら国々の分化が進み、これらの間の対立と相互浸透とが激しくなっている。
利潤率低下と利潤量増大との『相補性(相補関係)』の破れに伴う超過利潤獲得競争(グローバル)よって先進諸国の国内矛盾が爆発して、グローバル主義と保護貿易主義(関税主義など)が極めて深刻な政治的対立となり先鋭化している時代において、最先端産業の覇権争い、また局地紛争がますます頻発し、それらが大国間の戦争の誘発につながらないことを切に願うばかりである。各国の対立が進むといっても世界の国々で貿易なしで再生産が可能な国はほぼないであろう。ならば外交と交渉で平和的な解決に進むべきは当然の責務である。