「 阿蘇外輪山と『聖徳』―邪馬台国と俀国を求めて」
第一部 古代奈保里―阿蘇―高千穂(増補)
第二部 阿蘇外輪山と「聖徳」
佐藤彰著 発行2013年3月6日 価格2400円(税込) B6版429ページ
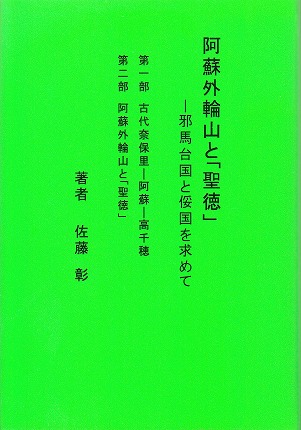
<本書の紹介>
[Ⅰ]本書は、邪馬台国と俀国の所在地の特定とその証明、および古代史の最大の謎である聖徳の存否と所在、その実像を重層的な論理構造と正反の事実の検証によって明証したものである。さらに俀国と日本国の攻防を追い、日本民族の形成史を明らかにしたものである。(1)本書は次に挙げる古代史の謎と真実を究明し、証明した。
1.邪馬台国と俀国の所在地を特定し、証明したこと。
2.卑弥呼の魏王朝への献上品・「絳青縑」は紫草の生産地・直入の生産物
3.魏王朝への献上品・短弓は古代鉄生産地・直入産(阿蘇火山産)
4.武磐龍と神武との関係
5.俀国天子・阿毎多利思比孤と物部との戦争、俀国の飛鳥間接支配と推古紀の謎の解明
6.聖徳の実在と所在地および没年の証明および業績
7.百済人僧侶・蓮城が聖徳の師・慧聡であること
8.倭王武の所在地と没年の解明
9.俀国と日本国との攻防と日本国による倭と俀国の併合
10.元興寺の豊国からの716年移築
11.欽明元年・532年および元興寺での仏教公伝・538年伝承の保存の必然性、
12.宇佐八幡神託事件の本質の解明 など
(2)本書の観点と方法については以下を御覧下さい。
「検証および認識深化の旅路」(2)
(旅の目的)
「後漢書」は、倭の国数について「通訳を連れて使者を送った国は三十ばかり」と書いている。魏志の時代でも、隋書の時代でも統治形態はかわっても地域的部族的な国々は続く。そのような国々の盟主が金印の倭奴国であり、次に魏志の邪馬台国であろう。隋書俀国伝には「(地方官に)軍尼(くに)百二十がいて、中国の牧宰(地方長官)のようなもの」とあり、神門神社の「綾布墨書」には、「白 西王城百北三十 国守」とある。
「隋書」の俀国(たいこく)伝には「邪靡堆が都でこれがいわゆる魏志の邪馬台である」と書いてある。邪馬台国の後継が俀国である。そのような邪馬台国と俀国の所在と実相の探求が本書である。
出版後、「阿蘇外輪山と聖徳」の検証と認識深化のため、いくつか旅をしてきた。旅には驚くことも多々あった。たとえば、豊後竹田の地元の紹介のパンフレットでは、会々の磨崖仏のひとつには「聖徳太子の16歳の時の像」とあり、天平の頃の作とあった。また初めての豊後大野の「蓮城寺」の史跡説明板では欽明と真野長者、聖徳との関係が示唆されているなど。驚きとともにそれらは、文献的に主として形成された本書の内容を実証しているように思われた。
「A列車に乗って『秦王国』に行こう」
今回は本書の「『秦王国』へ」を取り上げる。[第一部第1篇 魏志と隋書からの「邪馬壱国(台国)への行程」のⅠ.「隋書俀国伝の行程」 ☆『秦王国』へ (秦王国は日田か)]参照
1. A列車に乗って「秦王国」に行こう。
[ 第一部第1篇 魏志と隋書からの「邪馬壱国(台国)への行程」Ⅰ.「隋書俀国伝の行程」☆『秦王国』へ (秦王国は日田か)]
[本書α]
「秦王国」とは、「竹斯国からさらに東の所」にあり、その国から「また十余国を経て海岸に達する」という。このような地理的条件と「その住民が中国と同じで夷洲」、つまり徐福や夷洲という故事(秦文化)を連想させる地域で、弥生後期の文化が存在した地域とは、日田以外にはない。
[本書β]
「河童の伝承の源流は、熊本県の八代で、河童が呉から八代に来航したという言い伝えがある。河童一族が九千人、呉から八代にわたり、さらに筑後川に到り、水利事業に携わったという。」
「秦の発祥地は甘粛省東部で、秦族は馬の育成にすぐれていた遊牧民といわれ、西方の遊牧民との交易、西方の騎馬戦術を取り入れ、強力な国家に成長したといわれている。筑後川の田主丸の言い伝えでは、その来航者達を九千坊といい、中国大陸奥地のヒマラヤの麓からきたというから四川(劉備の蜀漢で有名)や天山山脈の麓(新彊省あたりか)からであろうか。秦の強大化にともなう進出地域でもある。
河童のお皿状の髪型は、秦支配下の遊牧民族の辮髪ではなかろうか。このような推理から河童祭りがある日田地域は中国から渡ってきた人、秦人の中心地域ではないかと推測する。」
<1>
(1) 秦という字の「はた」、「はだ」は、正確には「はだ」と読むそうである。しかし、大分県では「しん」というそうである。「シン」ならばまさに隋書の「秦王国」である。由布院や由布岳への経路として、別府や大分市にはよく行ったし、日田にも2回ほどいったが、秦という字を大分県では「しん」と読むことは知らなかった。
(2)
①羌族
秦の発祥地は甘粛省東部という。その甘粛省の西部には羌族がいた。羌は古代から辮髪であった。
中国西部を占める羌族は殷の時代、殷と対立していた。羌族は周と婚姻関係(姜)にあり、同盟関係であった。羌族は周と協力し、周は殷を滅ぼした。羌族出身の太公望は周から山東に封じられ、斉(羌斉)を建て、山東の斉は秦の始皇帝に滅ばされるまで続いた。
秦の発展につれて、甘粛省の羌はさらに西方に移動したり、四川、甘粛の羌族の地は秦に支配され、臣従した。秦漢が終わり、三国時代には四川、甘粛省の羌族は、魏と蜀との攻防において魏晋の傭兵として利用された。
五胡十六国時代に南安赤亭(甘粛省西)の羌が、後秦王朝を384年に長安にて建国したが、417年に滅ぼされた。羌族はチベット語族系である。
②月氏国→大月氏、小月氏
1) 敦煌辺りにいた月氏は、紀元前から甘粛省、西域、またモンゴル高原西半に勢力を保っていた。BC2世紀になると匈奴によって圧迫され、月氏の主勢力は、西域、モンゴル高原から退避、中央アジアに移動し、中央アジアのソグディアナに移住した。大月氏といわれ、漢の皇帝・孝文帝、紀元前180~紀元前157頃にはアフガン北部のバクトリアを滅ぼし、勢力を拡大した。
大月氏は三国時代に「親魏大月氏王」の印綬をもらう。 月氏の種族は不詳だが、敦煌地方時代は、トカラ語(インド・ヨーロッパ語族)といわれている。
(注) 昭武九姓の祖先は月氏で、甘粛省の昭武城に居たという。ソグディアナに移ってから、小国に分かれた。 その地の九国は、故地を忘れないように昭武の姓を名乗った。
昭武九国は南北朝時代にエフタルの支配下、隋の頃には西突厥に属した。昭武九姓の民はソグド人である
2) 甘粛省に残った一部の月氏は、青海省、チベット高原、崑崙山脈あたりで、羌族と混在し、同化して南山羌として小月氏となる。小月氏の各部族は荵罽羌、白馬羌、黄牛羌とよばれ、「魏略」には「有月氏餘種荵罽羌、白馬羌、黄牛羌」とある。
<2> (1)- A ((1)の続き)
[本書α]は、俀国への途中にある秦王国の特定である。隋書の行程からの特定であった。
秦という字は、日本書紀では「はだ」と読む。しかし大分県では「シン」というそうである。まさに秦王国である。インターネットの「秦の苗字の由来」サイトでは、秦は「西日本を中心に広くみられるが、大分県では「しん」と読む」とある。
大分県の秦「しん」を「同姓同名探しと名前ランキング」サイト(注)から地域別に並べてみる。
本書で秦王国の中心であるとする日田を基点にすると、日田市に10名、
日田市の西隣の浮羽(福岡県)には、112、
日田市の東の方に行くと、玖珠町5、由布15、別府31、大分市287、臼杵4、佐伯3、
日田から南に行くと、阿蘇2、竹田25、豊後大野32、
日田から北東に行くと日出町2、杵築17、国東22、宇佐4、中津5
以上を見ると日田を中心に東西に別れ、別府、大分市が最大の人数である。日田の南の阿蘇・竹田と豊後大野もかなり多い。
別府、大分市が最大の人数なのは、都市化の影響もあるだろう。阿蘇・竹田と豊後大野からは流出>流入で「秦人」がかなり居住していたと思われる。
(注)電話帳の掲載件数によるとする「同姓同名探しと名前ランキング」サイトは電話帳にのるものとして限定的なものであろうが、懐疑する理由も必要もないものである。
[本書β]は、田主丸辺りの「九千坊」こと「河童族」を自称する人々の伝承と私のコメントの混在である。本書βと上記の(2)の①羌族②「月氏国→大月氏、小月氏」とを比較対応させてみよう。
「河童のお皿状の髪型は、秦支配下の遊牧民族の辮髪」とは羌族は辮髪だったから対応しているようである。
「中国大陸奥地のヒマラヤの麓からきた」というのは、(2)の②の「月氏国→大月氏、小月氏」の2)「甘粛省に残った一部の月氏は、青海省、チベット高原、崑崙山脈あたりで、羌族と混在し、同化して南山羌として小月氏」の「南山羌」としての小月氏ともとれるし、後、秦に支配され、臣従した四川、甘粛の羌族ともとれる。
本書で繰り返し証明したように「俀国伝では、俀国の天子「阿毎多利思比孤」は「有阿蘇山」の俀国の都にいる。その地は邪馬台国とその後継の「阿蘇山あり」の俀国の都である。そこは「夜麻都」であり、「奈保里」である。」(第二部Ⅳ(Ⅱ)俀の天子の猪鹿狼寺と斑鳩寺の(加良登の宮殿の帝)など参照 )
筑後川の河川潅漑以外にも、当然にも秦人が都の「夜麻都」や「奈保里」の豊後竹田や豊後大野にも、職人、技術者として集まる。「秦の苗字の由来」のサイトをみても秦は日田の南の竹田、豊後大野、阿蘇にもかなり多い。(2)の②の2)「甘粛省に残った一部の月氏は、青海省、チベット高原、崑崙山脈あたりで、羌族と混在し、同化して南山羌として小月氏」となる。まさにヒマラヤの小月氏である。
小月氏の各部族は荵罽羌、白馬羌、黄牛羌とよばれ、「魏略」には「有月氏餘種荵罽羌、白馬羌、黄牛羌」とあると紹介したが、豊後竹田には「黄牛の滝」がある。小月氏の黄牛羌と竹田の「黄牛」とが対応するなら、秦王国の主な住民は、小月氏の黄牛羌であり、秦(しん)という名から秦支配下の秦人としての羌族か、後の羌族が建てた「後秦」である。(次回に続く)
テレビで「僕達急行A列車でいこう」という映画をみた。映画に「日田彦山線」というフレーズが一回出てきた。A列車とは今でもよく分からないが、映画にあやかって「A列車に乗って「秦王国」に行こう」とした。日田には久大線でもいけるが、小倉からいくと香春神社や宇佐神宮の由縁などにも触れることができる。次回は、「A列車に乗って「秦王国」に行こう」の続きで、大分県の秦「シン」と秦「はた」、「はだ」との区別の由来や漱石の宇佐八幡などを見てみる。
「読者の質問と著者からの返事」(2)
(今回の「読者からの質問」)
「法皇元年」はいつでしょうか。はっきり書かれてないように思われますが。
(著者からの返事)
1. 真野・物部戦争
第二部「5」の(1)相関からの分析と(2)擬似的例証で証明したように、「鏡当四年」584年に俀国の「阿毎多利思比孤」軍が、物部守屋と播磨で戦争し、物部守屋から播磨の領土を奪った。さらにその3年後の587年、阿毎多利思比孤は西からの「阿毎多利思比孤」軍、東からの蘇我軍とのはさみうちによって、物部守屋を滅ぼし、難波から葛城までを支配下においた。物部との戦争は、難波の港、葛城の鉄などの領地争いを本質としたものであったが、双方の宗教を掲げての戦争でもあった。(真野長者伝説によれば、丁酉・577年にも真野・物部戦争は瀬戸内海でもおこなわれ、此の時、降伏と和平の使者を物部側は豊後におくっている。)
2. ①死亡年月
私が「阿毎多利思比孤」=真野長者と証明した真野長者の死亡年月は、真野長者の伝承資料から海東諸国紀、襲国偽僭考(九州年号)などにある「聖徳」・「己丑」629年2月15日である(第二部のⅢの「阿毎多利思比孤―真野長者―聖徳」および「俀国天子・阿毎多利思比孤の没年、「己丑」の論証」参照)。
②聖徳諡号
阿毎多利思比孤は俀国天子であり、仏教興隆の祖であった。法隆寺金堂の「釈迦像光背銘」には、「上宮法皇」とあり、「上宮法皇」とは仏教興隆の祖であり、天子であった阿毎多利思比孤=真野長者であった。九州年号「聖徳」の「聖徳」とは、真野長者、すなわち俀国の天子・阿毎多利思比孤、および上宮法皇の没後の諡号でもあったのである。
③皇帝「位」の法皇寺
大分と臼杵の境の九六位(くろくい)に円通寺がある。伝承では崇峻四年(591年)建立という。
九六位(くろくい)は九鹿猪とも書きクシフルの地である。九六位(くろくい)は、周礼によれば陰陽九六数であり、皇帝の居所の方形数である。九六位(九鹿猪)は、文字通り、読み通りの地名「九六位」であり、皇帝「位」の居所であった。
九州年号「聖徳」に死去した「阿毎多利思比孤」=真野長者の法名は「慈老院殿円通慈観大禅門」である。真野長者の法名の「円通」から円通寺こそ、建通寺であり、またの名・法皇寺(同音・似音変換によって法興寺)である。
(注) 九六位 (九鹿猪)の円通寺の創建年(591年)が伝承通りとすると、菩提寺は、法皇寺である。
3.私が本書で証明したように、「阿毎多利思比孤」=真野長者の死亡年月は、海東諸国紀、襲国偽僭考(九州年号)などにある「聖徳」・「己丑」629年2月15日である。
「釈迦三尊像光背銘」にある「法興」あるいは「法興元世」という年号は、「二中暦」、「麗気記私抄」、「海東諸国記」、「和漢年契」、「襲国偽僭考」にはない。それは王法年号ではない。
「釈迦三尊像光背銘」にある「法興三十一年」あるいは「法興元世」という年号は、王法年号ではなく、天子が法王を兼ねた仏法表現で「法皇」→「法興」という同音・似音変換である。「法興三十一年」あるいは「法興元世」は、「法皇三十一年」あるいは「法皇元世」である。
「釈迦像光背銘」は、辛巳・621年の翌年・622年に夫人が死去し、その翌日「法皇登遐」としている。つまり「釈迦像光背銘」の現銘文によれば、上宮法皇の死亡年は、壬午(622年)二月二十二日である。しかし、「上宮聖徳法王帝説」は、「釈迦像光背銘」に対して「夫人の卒したまう日顕らか也。聖王の薨じたまう年月を注さず」といい、つまり「聖王」の没年干支および月がないといっている。「聖王」の没年干支は改竄されている疑いがある(注)。
しかし、「釈迦像光背銘」の「法皇登遐」の前年の、辛巳・621年は、「法皇三十一年」あるいは「法皇元世」である。「法興三十一年」なら遡って法興元の干支を推定でき、それは法興元を崇峻四年591年・辛亥である。そうすると、「円通」寺創建が591年という伝承と「釈迦像光背銘」の「法皇登遐」の前年の、辛巳からの逆算した法興元、崇峻四年591年・辛亥とは一致する。
すると、次のようにまとめ、推論する事ができる。「阿毎多利思比孤」=真野長者の法名が「慈老院殿円通慈観大禅門」であること、九六位(くろくい)は、周礼によれば陰陽九六数であり、天子(皇帝)の居所であることから、「九六位」の創建591年の「円通」寺は、法皇寺であり、同音・似音変換によって法興寺であり、法興元は591年の可能性が高いということである。奇しくも円通寺創建の崇峻四年(591年)は、隋の文帝が「三宝興隆の詔」を出した年である。「十七条の憲法」には、「二曰。篤敬三宝」とある。
以上の推論から、法皇寺=「円通」寺(創建591年)で、法興元は591年の蓋然性が高い。
(注)「釈迦像光背銘」は鍍金後に鐫刻されているので、追刻の可能性があるという。天平八年二月二十二日行信が令旨によって法華経を講読した以前か以後に造作や改竄の疑いがある。
4. 法興元・591年から法興六年は596年(推古四年)となるが、法興六年に
(A)風土記「伊豫国」逸文によると上宮聖徳皇が師である高麗慧慈(日本書紀推古三年595年帰化?)等と「逍遥夷與村」とある(「釈日本紀」に記録された碑文には、なぜか「侍高麗慧聡僧。葛城臣等也」とある)。
(B)真野長者伝説にも、真野長者が、伊予の地に般若姫の菩提を弔うために、「多くの家来やお供達、さらに蓮城法師とともに二千人の規模、大小の船二十五艘に乗り、三月に出航いたしました。」(「真名野長者物語」小川隆平訳注釈 )とある。
風土記「伊豫国」逸文や「釈日本紀」にある「逍遥夷與村」の記事(A)と真野長者伝説の記事(B)とは、「阿毎多利思比孤」=真野長者が上宮聖徳皇なら同一事件であるが、詳細が錯誤などで違いがある。
詩文は、「阿毎多利思比孤」=真野長者が上宮聖徳皇なら、真野長者の伊予巡行の時の詩文であろう。
「釈日本紀」には、「逍遥夷與村」は法興六年十月とあるが、詩文には「椿樹」とあり、季節があわない。真野長者伝説には「三月」とあり、真野長者の伊予巡行は3月である。椿の季節である。詩文には椿の花が書かれてある。法興六年十月とある「釈日本紀」の「逍遥夷與村」では詩文の季節にあわない。
「逍遥夷與村」のお供は、風土記「伊豫国」逸文の「高麗慧慈」、「釈日本紀」では「侍高麗慧聡僧。葛城臣等也」とある。真野長者伝説では、百済人の「蓮城法師」である。蓮城法師は、南朝時代の高僧である恵思大師の弟子で、中国の蓮城からきたので、地名から蓮城法師と呼ばれている。恵思大師は南豫州(河南省上蔡県)出身で、上蔡県は河南省駐馬店市である。地名・蓮城は河南省許昌市の別名であり、河南省駐馬店市とは現在の地図では約133kで近隣である(注1)。
元興寺の僧正達は、「陪豊前禁内講三論文」であった。したがって建興寺(あとの元興寺)は豊国にあった(注2)。蓮城法師は、地名から蓮城法師と呼ばれているが、本来、恵思の弟子であるから、「恵」がつく名であろう。しかも、(B)記事の記載から蓮城法師は真野長者の伊予巡行にお供をしており、さらに(B)と(A)とは同一事件だから、百済人・蓮城法師は、聖徳の師の慧聡のことである。「東大寺具書」にある「・・・・陪豊前禁内講三論文。百済恵宗法師又以同之。・・・」の「百済恵宗法師」のことである。
したがって、「侍高麗慧聡僧。葛城臣等也」とある「高麗慧聡僧」の「高麗」は錯誤である。「高麗慧慈」がお供をしたかどうかは分からないし、「高麗慧慈」の真相は分かりにくい。
(注1)恵思大師が修行したのは光州の大蘇山といわれ、河南省商城県辺りといわれる。恵思大師の出身地・河南省駐馬店市上蔡県にも大蘇という地名がある。阿蘇の産山近くにも大蘇がある。
(注2)元興寺縁起では、「建興」と「建通」、それに「法皇」の「三称名」を「永世」に「流布」せよと言っている。「法皇」とは、「建興」と「建通」の時代のことである。建興と建通、それらの寺は俀国にあった。法皇とはそこの仏教興隆の祖であり、天子である。
元興寺の僧正達は、「陪豊前禁内講三論文」であった。元興寺、元の名は建興寺も大分市の向原地域や向之原にあったとすると「丈六光銘」の「戊辰(608)、大隋国の使主、鴻艪寺掌客裴世清、使副・尚書・祠部・主事・遍光高来たりて之を奉ず」の後の次の記載、「明年己巳(609)四月八日甲辰、畢竟、元興寺に座す」とは、この地の元興寺となり、俀国伝の隋使の行路とも一致する。かつ「等與刀禰禰(ネネ)大王」とは、隋書の俀国の天子、「阿毎多利思比孤」となる。元興寺の本尊収納は丈六光銘のいう「己巳・609年」となり、推古十四・606年「本尊」収納とはちがったこととなる。
以上
なお、前回の(今回の「読者からの質問」)に対する(著者からの返事)を理解しやすいように本書第一部第2篇Ⅱの「(二)邪馬台国と年代的証明」を紹介しておきます。
Ⅰ.「読者の質問と著者からの返事」
(今回の「読者からの質問」)
①第一部第2篇「Ⅱ.魏志倭人伝と景行、仲哀、神功紀」の(二)「邪馬台国と年代的証明」(P.六四)にある「景行56年、成務4年、仲哀9年」が分かりません。
②景行元年の算出において、景行56年、成務4年、仲哀9年となっていますが、講談社学術文庫の日本書紀では景行、成務ともに在位期間は60年となっています。その根拠が分からず、私は著者が干支1運短くされたのだろうと勝手に判断したのですが、景行、成務合わせて60年とされた理由を書かれた方が分かりやすいです。
(著者からの返事)
「景行56年、成務4年、仲哀9年」が分からないという意見や質問がありました。説明を省いていたのを反省しています。
景行56年、成務4年、仲哀9年は根拠ある仮定です。古事記では景行の九州遠征記事がなく、熊襲との戦争が反映されていません。したがって古事記はとりあげることもできません。
不名誉にも熊襲に負けて死亡したらしい仲哀の生存年数および在位期間9年は実在的意味があります。一方、日本書紀での景行、成務のそれぞれの生存年数は、全くあてになりません。したがって在位期間の事跡年数が問題になります。
景行の在位期間は60年間となっていますが、事跡らしい記事は56年間です。さらに宇佐公康著「古伝が語る古代史」によれば、景行天皇は高森の隣の蘇陽町で死亡したとの宇佐家の伝承があるので60年は、妥当以上に過大です。
①成務の事跡らしい記事は5年間です。事跡の内容は稲置、都督記事など作文で疑わしいと見て、景行60年を景行+成務(0年)とすると、景行60年+仲哀9年=69年となり、怪しい数字ながらもすっきりしますが、成務を全く無視するようですっきりしません。
②成務は、日本書紀が記載している以上、在位を0とするわけにもいきませんので、形而的に0〈成務〈5です。仲哀9年間は、絶対に動かせません。
簡単な辻褄合わせをします。景行60年を60X+α(正確な年数)と仮定し、妥当な数として事跡年数56年間を与えます。すると、60X+α=56は、Xは1でα=-4。こうして景行の日本書紀の在位期間から4年引きます。そこで、成務の事跡は乏しいとして、0〈成務〈5 の中から在位年数を任意定数とみなして適切な数を取ります。
仲哀は福岡県あたりで熊襲に殺されており、事跡の実在性は間違いがないので、仲哀死=神功1年、320年。
これと整合するように、成務在位年数は、〈5の任意定数なので、適切な数4をとることができます。任意定数は整合し、説明がつけば適切にとれるからです。これで、神功の前三代は、景行56年間、成務4年間、仲哀9年間で計69年間となります。こうして適切な数をとることによって、辻褄合わせから、根拠あるものとなります。
これを邪馬台国と対立する一国の紀年とすると神功1年は、320年だから、320-69=251年頃、景行の元年となる。景行56年間、成務4年間、仲哀9年間で計69年間は、合理的なもので、かつ「(二)邪馬台国と年代的証明」の論旨の全体とも整合します。(以上)
Ⅱ.「阿蘇外輪山と『聖徳』」の「検証および認識深化の旅路」
「欽明の牟久原殿」
1.この著作は、「欽明元年・532年および元興寺での仏教公伝・538年伝承の保存の必然性」および「元興寺の豊国からの716年移築」を証明した。
元興寺縁起では欽明は、後宮の牟久原殿を他国の神(仏像)の宮としたとある。後宮とは、巫女が天と交感し、始祖・先祖を祭祀するフル(場所)で、もともとは神殿でもあったろう。神殿の牟久原殿を「他国の神(仏像)」の宮としたというのであるから、欽明の大変革であった。
問題は、牟久原殿がどこにあったかである(注)。
「牟久原殿」とは、葦北にも「向久原」があるが、私は額田部一族がいた葦北の向久原であるとこの著作で書いた。なぜなら、推古は幼名・額田部といい、その息子・竹田皇子と後から合葬されたらしい墳墓には、阿蘇ピンク石石棺が運ばれており、埋葬様式が似ることになるからである。葦北の「向久原」には欽明の後宮があって、推古も若い時代居住していたと私は推理した。「牟久原殿」という神殿かつ後宮を欽明は寺に変えたのである。
欽明の時代・538年仏教公伝当時「牟久原殿」の所在は、芦北、益城あたりにあった。
呉人で元興寺の僧、福亮は、俗姓・熊凝氏という。私は、万葉集に出てくる大伴君熊凝は、火の益城郡が出自なので、福亮が熊凝氏ならば、福亮は火の益城郡の熊凝にいたとした。そして牟久原殿とは、葦北の向久原とした。
2. 海の底沖つ白波 竜田山いつか越えなむ 妹があたり見む(万葉集巻第一 八三)
朝霞やまず棚引く竜田山 船出せん日にわれ恋ひむかも(巻第七 一一八一)
奈良には、竜田地名はあるが、竜田山はない。しかも、奈良の竜田からは難波津はみえない。古代、熊本市の竜田山の西は海であった。
「三四郎は宿帳を取り上げて、福岡県京都郡真崎村小川三四郎二十三年学生と正直に書いたが、女のところへいってまったく困ってしまった。」という京都郡出身の小川三四郎は美禰子と出会うことになる大学の池のそばで「熊本の高等学校にいる時分もこれより静かな竜田山に上ったり、月見草ばかりはえている運動場に寝たりして、まったく世の中を忘れた気になったことは幾度となくある、けれどもこの孤独の感じは今はじめて起こった。」(夏目漱石「三四郎」)。三四郎は竜田山に幾度か上ったということである。
万葉集巻五には旅人の送別会の歌群の中に
人もねのうらぶれをるに 竜田山御馬 近づかば忘らしなむか という歌が松浦佐世姫の歌群の後にある。
私は上の歌の竜田山は、熊本市の竜田山ではないかと思っている。この歌こそ大伴君熊凝の歌ではないかと思っている。奈良には、竜田の地名はあっても竜田山はないからである。熊本市の竜田山の西は、古代は海であり、竜田山を越えると、南は益城郡と葦北である。益城郡の大伴君熊凝にふさわしい。
下益城郡に隈庄町があった(現、熊本市南区城南町隈庄あたりか)(注2)。その地こそ「熊凝」という地にピッタリとあう。
しかし、大伴君熊凝の熊凝の地が即、「牟久原殿」や元興寺の所在地とは限らない。ある読者が「向久原」を探したが分からなかったといっていた。そんなはずはないと思って「google map」で探すと見あたらなかった。
私の言う「益城郡の熊凝」(城南町隈庄あたり)から八代海の方向へ南西に下ると、20年前の地図でも向久原や向久原川が載っている。「google map」では、現在の熊本県宇城市松橋町曲野の道徳山公園辺りである。ここが欽明の「牟久原殿」である。
この「向久原」の続きの益城郡には「豊秋」と「秋津」という地名があり、近くに井寺古墳という装飾壁画古墳がある。この時期、装飾壁画古墳と石人、石馬で代表される火、筑紫の文化と大和とは、全く異なる文化であった。欽明は、この地の「牟久原殿」で宗教革命を行なったのである。
3. 欽明は「都を倭国の磯城郡の磯城嶋に遷す」(欽明紀即位元年)という。「磯城嶋の金刺宮」とあるが、「日本」ではなく「倭国」とある。「都を倭国の磯城郡の磯城嶋に遷す」の「倭国」とは「旧唐書」の「倭国」である。益城郡には地名「豊秋」、その隣接に「秋津」があり、まさに「豊秋津」である。旧唐書の倭国と日本国との区別および葦北の西部(さいふ)という地名から、仏教公伝の西部姫氏達率怒唎斯致契の西部姫氏とは、九州・倭国の「東海姫氏国」の姫氏の一族とすると、仏教公伝552年は倭国から日本国・飛鳥への仏教公伝である。
(注2)隈庄は延喜式の球磨駅という説もある。
本文紹介(2) 2014年5月7日
今年3月、この著作で聖徳の師・慧聡であることを証明した百済人・蓮城の名のつく蓮城寺に行った。その機縁でいただいた「豊後大野GEOフォトブック」に地域芸能として「白熊・羽熊」の記述があった。「この芸能のそもそもの発祥は不明であるが・・」とあり、市内に「白熊と表記する団体」と「羽熊と表記する団体」があるという。私が邪馬台国の「一大卒」とする羽白熊鷲の「白」をとれば「白熊」になるし、「羽」をとれば「羽熊」となる。大変、面白いことなので、第一部の「(一)景行紀と邪馬台国」の中の「羽白熊鷲は、魏志倭人伝の一大卒」を紹介する。
次に、武磐立系の勢力圏である直入地域と西都原地域との直近、同族関係を背景にして書いた、第一部[補論4―存在しない年号の紀年鏡と邪馬台国について]を紹介する。豊後竹田の扇森山横穴古墳の横矧板鋲留短甲と全く同工のものが、宮崎県西都市西都原地下式横穴4号で発見されていることをつい最近知った。